京都観光に関するプロモーション広告が表示されています
京都の世界遺産「東寺(教王護国寺) 」の見どころとは?
京都旅行の見どころといえば、東寺の五重塔ではないでしょうか?京湯元 ハトヤ瑞鳳閣から徒歩15分の場所にある東寺は、世界遺産にも登録されている歴史ある寺院です。全国から多くの人が訪れる東寺は、春と秋に期間限定のライトアップが行われ、枝垂れ桜や紅葉が人々を魅了します。この記事では、東寺の見どころや魅力について紹介します。
東寺は誰が建てた寺院?
東寺は真言宗の総本山であり、正式名称は「教王護国寺」読み方は「きょうおうごこくじ」です。東寺は桓武天皇によって796年に創建されました。都を守ること(国家鎮護)が目的だったため、創建当時は西と東の2か所に寺院が建てられていました。東の寺院は東寺(とうじ)、西の寺院が西寺(さいじ)と呼ばれていたことが、「東寺」と呼ばれる由来です。その後、823年に嵯峨天皇が東寺を弘法大師(空海)に下賜しました。西寺は1233年に焼失したため、現在、目にすることができるのは東寺のみです。
五重塔
新幹線で京都に到着する際、南に見える高い塔が京都のシンボルともいえる東寺の「五重塔」です。塔の高さは約55mで、木造の建築物としては日本一の高さを誇ります。五重塔は、仏陀の遺骨を安置するストゥーパ(仏塔)が起源とされ、東寺の五重塔には、当時弘法大師空海が唐より持ち帰った仏舎利が納められました。塔内部には仏像や経典も安置されており、仏教文化の豊かさを感じることができます。春の特別公開などでは、この五重塔へ入ることもできます。
春のライトアップ
東寺は春と秋に期間限定でライトアップが開催されます。春は境内に多くの桜が咲くため、幻想的で美しい景観を楽しめることが魅力です。夜の闇に浮かぶ桜と歴史を感じさせる建造物は、日中とは異なる景観で人気があります。
東寺の見どころの一つが、大きな紅しだれ桜「不二桜(ふじざくら)」です。不二桜は、もとは東北の盛岡にありましたが、秋田、三重を経て、京都の東寺へと移植されました。樹齢120年、樹高13m、枝張り10mの桜が満開となる様子は壮観です。
拝観は午後の6時から開始されますが、日曜日や祝日には多くの観光客が、不二桜や境内のライトアップを一目見ようと長い列を作ります。待ち時間を短くしたい場合は、なるべく遅い時間に行く方がスムーズに拝観できるためおすすめです。拝観時間は午後9時30分(受付は午後9時まで)ですので、午後8時以降に受付して入場するのが良いでしょう。春の夜は冷えるため暖かい服装がおすすめです。
秋のライトアップ
秋のライトアップは、色とりどりに紅葉した木々と五重塔が池に写り大変綺麗です。こちらも人気のスポットとして多くの観光客が訪れます。
東寺ライトアップ期間の駐車場について
特別拝観中の駐車場利用料金は特別料金となる場合があります。比較的大きな駐車場ですが、満車の場合は周辺にコインパーキングがあるので、そちらを利用することも可能です。事前にいくつか候補を探しておくと安心です。
東寺の駐車場入口は敷地の東側、大宮通り沿いにあり少しわかりにくい場所にあります。カーナビや地図アプリなどで行く場合、目標として「東寺前交番」とする方法もおすすめです。
駐車料金
・大型バス 2,000円/2時間
・自家用車、タクシー 600円/2時間
2時間以降は1時間ごとに300円
・バイク 200円/2時間
2時間以降は1時間ごとに100円
※新春特別拝観時(1/1~1/5)
駐車料金 自家用車 1,000円 大型バス 3,000円
東寺のパワースポット/天降石
「天降石」は、食堂(じきどう)の西側、毘沙門堂の横にあります。天降石は、石を撫でた手で、体の悪い場所をさするとご利益があると伝えられています。江戸時代には「不動石」「護法石」「五宝石」などの名称がありましたが、現在は「天降石」と呼ばれています。
東寺のパワースポット/尊勝陀羅尼の碑
「尊勝陀羅尼の碑」は、天降石の左側2つ目の石碑です。大きな石碑を背負っている亀のような生物は伝説上の贔屓(ひいき)という生き物です。石碑にある尊勝仏頂の悟りや功徳 (くどく) を説いた陀羅尼を読誦 (どくじゅ) すると、罪障消滅や除災・延寿の功徳があるとされています。この石碑を回りながら、石像の頭や手足などを撫で、その手で自分の悪い場所を擦るとご利益があるそうです。御影堂や毘沙門堂で「万病ぬぐいの布」を購入して贔屓を擦り、その後に体の悪い部分を擦る方法もあります。
東寺の開門は早朝5時です。春や秋のライトアップなど、観光シーズンは国内外から来る観光客でにぎわいますが、朝は人が少なく、広い境内をゆっくりと散歩することができます。
南大門(重要文化財)
九条通に面しているのは南大門です。その昔は仏師運慶・湛慶作の仁王像が祀られていましたが明治頃に焼失し、明治28年、平安遷都1100年記念として、三十三間堂の西門を移築し再建しました。幅が約18m、高さは約13mあり、桃山時代に建築された重要文化財です。
金堂(国宝)
金堂は東寺の本堂ですが、1486年に焼失したため、1603年に豊臣秀頼によって再建されました。外観は一重裳階(もこし)付きと呼ばれる特殊な建築です。宋の様式、和様と大仏様(天竺様)が取り入れられています。金堂内には、本尊の薬師如来坐像と日光菩薩、月光菩薩の両脇侍像が安置されていて、常時公開されています。
講堂(重要文化財)
東寺の中心に位置する講堂は、弘法大師の密教の教えを表しているといわれています。講堂に安置された大日如来は、宇宙の中心とされ、整然と安置された全部で21体の彫像は、羯磨曼荼羅(立体曼荼羅)を構成しているのだそうです。
御影堂(国宝)
御影堂とは、かつて弘法大師空海が住房としていた「大師堂」とも呼ばれる境内西北部に建つ住宅風の仏堂を指します。前堂(まえどう)、後堂(うしろどう)、中門(ちゅうもん)からなる複合仏堂で、全体を檜皮葺(ひわだぶき)した重厚感のある建物です。北側の前堂には弘法大師坐像(国宝)が安置され、毎朝6時に「お大師様」に朝食を捧げる「生身供」(しょうじんく)が執り行われ、多くの参拝者が集まります。
御守りと御朱印
ここでは東寺の御守りと御朱印をご紹介します。
東寺のお守り
東寺のお守りには、学業成就や縁結び、交通安全などのご利益があるといわれています。通常の御守や指輪タイプ、ストラップタイプなどから選ぶことが可能です。価格は500円~1,000円ほどです。東寺のお守りは、食堂や拝観受付横など境内各所の売店で購入できます。
東寺の御朱印
東寺の納経所(朱印所)は、食堂の中にあります。9種類あり、東寺のご本尊である薬師如来や弘法大師の御朱印が人気です。志納金は300円です。
東寺の拝観料
東寺の拝観料は、季節やイベントにより変動します。
・境内は無料
・御影堂、食堂などの拝観は常時無料
・金堂・講堂、観智院は常時公開(有料500円~800円)
・五重塔初層内部や宝物館内部は特別公開期間中のみ公開(有料500円~800円)
・共通券1,000円~1,300円
・ライトアップ1,000円
東寺へのアクセス
東寺は京都駅より徒歩で約15分。 近鉄東寺駅からでも10分ほどの位置にあり、駅に近いのでアクセスも大変便利です。
まとめ
東寺の魅力や見どころについてご紹介しました。東寺は春や秋の特別拝観が人気ですが、初夏の新緑が美しい季節や、冬の雪景色の中で見る東寺もおすすめです。混雑する時期を避け、四季折々の東寺を楽しむのも良いのではないでしょうか?
京湯元 ハトヤ瑞鳳閣は、京都駅周辺で唯一の天然温泉を持つホテルです(※)。プライベート温泉付きの客室もございます。京都駅から徒歩5分、東寺へは徒歩15分とアクセスも良好なため、グループや家族旅行にもおすすめです。旅行の拠点ホテルとして、ぜひ京湯元 ハトヤ瑞鳳閣をご活用ください。
※2025年1月現在
京湯元 ハトヤ瑞鳳閣
-INFO-
京湯元 ハトヤ瑞鳳閣
住所:京都府京都市下京区西洞院通塩小路下ル南不動堂町802
営業時間:24時間(フロント)、カフェ8:00~18:00、Bar 17:00~2:00
定休日:年中無休
予約可否:可
※記事の内容は2025年1月時点の情報のため、予告なく変更になる可能性があります。お出かけ前には公式サイトで最新情報をご確認ください。

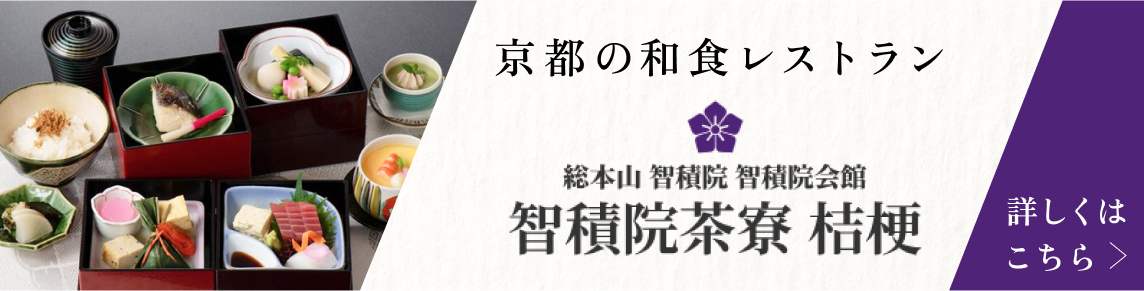
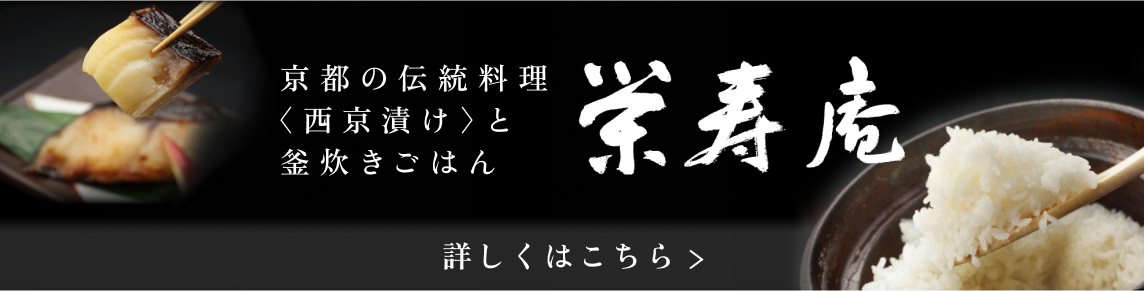

コメント